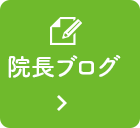2025.04.16

百日咳が流行しています。 New!
乳児期早期から罹患する可能性があり、1歳以下の乳児、特に生後6カ月以下では死に至る危険性も高いといわれています。
【感染経路】飛沫感染により気道に侵入し、7-10 日間程度の潜伏期を経て発症します。
【症状】百日咳の臨床経過はカタル期と痙咳期と回復期の3期に分けられます。
1.カタル期(約2週間持続);通常7~10日間程度の潜伏期を経て、普通のかぜ症状で始まり、次第に咳の回数が増えて程度も激しくなります。この時点では百日咳かどうか症状だけではわかりません。
2.痙咳期(約2~3週間持続);次第に特徴ある発作性けいれん性の咳(痙咳)となります。これは短い咳が連続的に起こり(スタッカート)、続いて、息を吸う時に笛の音のようなヒューという音が出るようになります(笛声:whoop)。この様な咳嗽発作がくり返すことをレプリーゼといいます。嘔吐を伴うこともあります。
発熱はないか、あっても微熱程度で、息を詰めて咳をするため、顔面の静脈圧が上昇し、顔面浮腫、点状出血、眼球結膜出血、鼻出血などが見られることもあります。夜間の発作が多く、年齢が小さいほど症状は非定型的であり、乳児期早期では特徴的な咳がなく、単に息を止めているような無呼吸発作からチアノーゼ、けいれん、呼吸停止と進展することがあります。合併症としては肺炎、脳症があり、特に乳児で注意が必要です。1992~1994年の米国での調査によると、致命率は全年齢児で0.2%、6カ月未満児で0.6%といわれています。
3.回復期(2、3週~);激しい発作は次第に減衰し、2~3週間で認められなくなりますが、その後も時折忘れた頃に発作性の咳が出て、約2~3カ月で回復します。
成人の百日咳では咳が長期にわたって持続しますが、典型的な発作性の咳嗽を示すことはなく、やがて回復に向かうため、診断されにくいですが、菌の排出があるため、ワクチン未接種の新生児・乳児に対する感染源として注意が必要です。また、アデノウイルス、マイコプラズマ、クラミジアなどの呼吸器感染症でも同様の発作性の咳嗽を示すことがあり、鑑別診断上注意が必要です。
百日咳の特徴的症状
・夜間の咳
・特徴的な咳 Whooping、staccato
・咳込み時の嘔吐
・顔面の浮腫
・目の充血
【治療】百日咳の治療法には、百日咳菌に対する治療と咳に対する治療があります。
百日咳菌にはマクロライド系抗生剤が用いられます。5日間の服用で菌はほぼ消失します。
咳は、百日咳菌から出される毒素が原因となりますので、毒素の活動がおさまるまで待つ必要があります。
抗生剤は除菌することは可能ですが、毒素に対しては効果がありませんので、咳への対処療法として、鎮咳去痰薬や気管支拡張薬を使用することがあります。
一番重要なのは、ワクチンによる予防になります。
【予防】百日咳には効果的なワクチンがあります。
百日咳は百日咳菌が産生する毒素(Toxin)によって病気が発症するため、Toxin-mediated diseaseとも言われます。毒素に対する抗体により発症を防止できるために、百日咳ワクチンは、百日咳(PT)毒素と接着因子(FHA)毒素に対する免疫を獲得する成分が主体となっています。
百日咳ワクチンを含むDPT三種混合ワクチン(ジフテリア・百日咳・破傷風)あるいはDPT-IPV四種混合ワクチン(ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ)、令和6年度からはDPT-IPV-Hib 五種混合ワクチン(ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)の接種により、百日咳の発生数は激減しています。百日咳ワクチンの免疫効果は4~12年で減弱し、最終接種後時間経過とともに既接種者も感染するといわれています。そのため、小学校就学前にワクチン効果が薄まるため、日本小児科学会では任意での三種混合ワクチンの2回追加接種を推奨しています(① 学校就学前の1年間、②11-12歳)。
以上、簡単ですが百日咳について解説させていただきました。
重要なのは重症化しやすい乳児に感染させないように、周囲の方(両親、兄弟姉妹)が感染しないこと、つまり、予防接種(就学前、小学校6年での任意接種)と感染対策をしっかりするということですね。
ブログはこちら